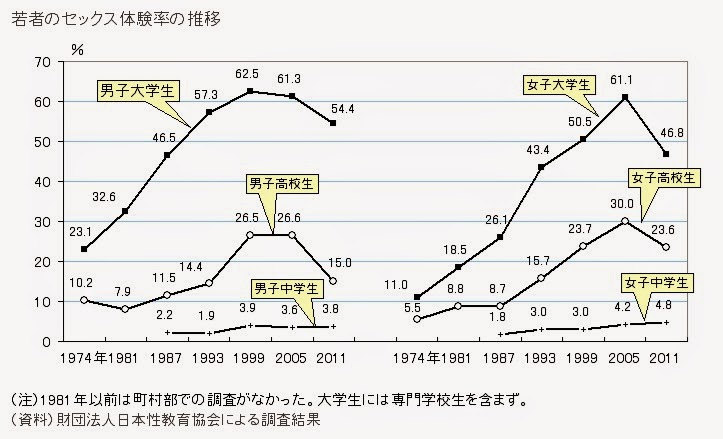今日は猫の日。
ところで突然ですが、猫と関わりの深い寄生性の単細胞生物があります。それが『トキソプラズマ』です。
1.トキソプラズマとは
世界中で見られる感染症で、世界人口の3分の1が感染していると推測されている。有病率には地域で大きな差がある。ガーナでは92%もありますが、日本では20~30%と推定されています。
健康な成人の場合には、感染しても無徴候に留まるか、せいぜい数週間のあいだ軽い風邪のような症状が出る程度でありますが、重症化した場合には、脳炎や神経系疾患をおこしたり、肺・心臓・肝臓・眼球などに悪影響を及ぼします。予防するためのワクチンは現在ありません。
2.猫とトキソプラズマの関係
寄生生物の中には、複数の動物の体内を往来しているものが少なくありません。トキソプラズマも複数の動物を経由しますが、その最終目的地が正に「猫」なのです。 トキソプラズマは、猫の体内に入ることで初めて有性生殖を行うことが出来ます。これにより、「オーシスト」と呼ばれる卵のような耐久性の強い形態となり、糞便として外界に排出されます。その糞便をネズミ等が摂食したり、土壌の中に溶け込んで植物や水を汚染することで他の生物の体内に入ります。
 3.「じゃあ、猫は危険?」「いいえ、まず感染しません!」
3.「じゃあ、猫は危険?」「いいえ、まず感染しません!」まず、猫と触れるだけで感染するわけではないことは明確です。感染猫がオーシストを排出するのは初感染の際の数週間に限られており、オーシストを排出しているのは猫の1~2%程度に過ぎません。また猫の糞便中のオーシストも成熟するのに数日を要することから、通常の飼い猫であれば飼い主が1~2日毎にトイ レ掃除をしている為、まず感染することはありません。
飼い猫の場合は、トイレ掃除を怠って糞を長時間放置した時に感染のリスクが発生します。
また、公園の砂場等に放置されている野良猫の糞には注意が必要でしょう。
また、公園の砂場等に放置されている野良猫の糞には注意が必要でしょう。
4.宿主の行動の変化
トキソプラズマが宿主にどのような影響を与えるかは、研究がまだあまり進んでいないようですが、いくつかの研究報告があります。
(1)トキソプラズマに感染したマウスはネコを恐れなくなる。また、猫の尿の匂いに引き寄せられるようになる。
これはネコを終宿主とするトキソプラズマの巧妙な戦略です。あの『トムとジェリー』もトキソプラズマによって引き起こされたストーリーだろう、と私は思っています…。
(2)トキソプラズマの慢性感染によりヒトの行動や人格にも変化が出るとする研究例はかなりあります。
・統合失調症や双極性障害にかかりやすくなる
・男性は、リスクを恐れなくなる・集中力散漫・規則破り・危険行為・独断的・反社会的・猜疑的・嫉妬深い・女性にもてない
・女性は、社交的・ふしだら・男性にもてる
男性酷いな(笑)。オタク系の男子に猫好きが多いのは、トキソプラズマで説明できるかもしれません。
(3)トキソプラズマが宿主の行動を操作する手段としては、脳内麻薬である「ドーパミン」が使用されているとみられている。宿主が、トキソプラズマにとって都合のよい行動をしたときに、報酬としてドーパミンが与えられる。
 寄生生物は、自然界には当たり前のように存在しており、自分より大きな生物の行動をいとも容易くコントロールしています。それは、人間も例外ではないと考えた方が自然です。
寄生生物は、自然界には当たり前のように存在しており、自分より大きな生物の行動をいとも容易くコントロールしています。それは、人間も例外ではないと考えた方が自然です。
私が猫の柔らかいおなかに顔を埋めるのも、トキソプラズマが引き起こしている行動なのかもしれません。
トキソプラズマが宿主にどのような影響を与えるかは、研究がまだあまり進んでいないようですが、いくつかの研究報告があります。
(1)トキソプラズマに感染したマウスはネコを恐れなくなる。また、猫の尿の匂いに引き寄せられるようになる。
これはネコを終宿主とするトキソプラズマの巧妙な戦略です。あの『トムとジェリー』もトキソプラズマによって引き起こされたストーリーだろう、と私は思っています…。
(2)トキソプラズマの慢性感染によりヒトの行動や人格にも変化が出るとする研究例はかなりあります。
・統合失調症や双極性障害にかかりやすくなる
・男性は、リスクを恐れなくなる・集中力散漫・規則破り・危険行為・独断的・反社会的・猜疑的・嫉妬深い・女性にもてない
・女性は、社交的・ふしだら・男性にもてる
男性酷いな(笑)。オタク系の男子に猫好きが多いのは、トキソプラズマで説明できるかもしれません。
(3)トキソプラズマが宿主の行動を操作する手段としては、脳内麻薬である「ドーパミン」が使用されているとみられている。宿主が、トキソプラズマにとって都合のよい行動をしたときに、報酬としてドーパミンが与えられる。
 寄生生物は、自然界には当たり前のように存在しており、自分より大きな生物の行動をいとも容易くコントロールしています。それは、人間も例外ではないと考えた方が自然です。
寄生生物は、自然界には当たり前のように存在しており、自分より大きな生物の行動をいとも容易くコントロールしています。それは、人間も例外ではないと考えた方が自然です。私が猫の柔らかいおなかに顔を埋めるのも、トキソプラズマが引き起こしている行動なのかもしれません。